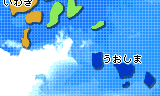|
県が策定した市町村合併推進要綱の中心となる合併パターンの概要によると、現在の70市町村を11に集約する基本パターンと、それ以外にその他として15の組み合わせを示しています。上島地区は、二つのパターンがあり、基本パターンでは今治市と越智郡15ヶ町村の組み合わせに含まれており、参考パターンでは上島地区4ヶ町村の組み合わせとなっています。
しかし、これは愛媛県が地元の合併についての気運を盛り上げるために、望ましいと思われるパターンを示したもので、これだけにとらわれる必要もなく、あくまで合併は地元の自主的な判断で決定すべきものです。
なお、県が示したパターン以外にも、例えば上島と越智郡島しょ部、上島と因島市などの組み合わせも考えられますが、このように多くの選択肢があるということは、いずれも可能性を有すると同時に決め手にも欠け、この問題がそれだけ難しいということです。 |
|