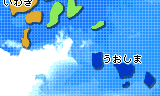| 協定項目 |
内容・備考 |
| 12 |
特別職の身分の取扱い |
常勤特別職(4役など)
非常勤特別職(教育委員、選挙管理
委員など)
| [備考] 首長をはじめ特別職は全員失職することとなる。こうした特別職の職員の処置について、協議会で協議する必要がある。 |
|
| 13 |
条例・規則の取扱い |
市町村の条例、規則
| [備考] 町村が消滅すれば条例・規則はすべて失効するので、新町の条例・規則を制定する必要がある。 |
|
| 14 |
機構及び組織 |
行政組織・機構
| [備考] 新町の条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。 |
|
| 15 |
一部事務組合の取扱い |
上島上水道企業団、上島地区衛生事務組合(越智郡島部消防事務組合、越智郡老人ホーム組合)
| [備考] 合併が行われた場合は、町村の法人格が消滅するため、組合も消滅し、新町の事業に組み入れられることとなる。なお、広域(郡単位)のものについては、各町村が脱退し、新町で加入することとなる。 |
|
| 16 |
使用料、手数料の取扱い |
各種施設使用料、戸籍等の手数料など
| [備考] 各町村間の同一目的の施設や事務について、使用料が違う場合は、予めその取扱いについて調整しておく必要がある。 |
|
| 17 |
公共的団体の取扱い |
消防団、社会福祉協議会、商工会等
| [備考] 合併後、新町としての一体感を醸成する意味からも統合されるのが理想的であり、これら団体ごとへの働きかけの基本方針について協議することとなる。 |
|
| 18 |
行政連絡機構の取扱い |
自治会制度や納税組合制度など
| [備考] 行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、合併後のあり方を協議する。 |
|
| 19 |
町字名の取扱い |
同一町、字名などの調整
| [備考] 住民の愛着があるものであるため、従来どおり存続させる場合が多い。郵便等の混乱を避けるための調整が必要である。 |
|
| 20 |
慣行の取扱い |
町村章、村民憲章など
| [備考] 町村民憲章、花、木、祭り等の各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきが強いため、合併後も引き継がれるものである。 |
|
| 21 |
その他
(各種事務事業の取扱い) |
議会、総務、企画、財政、会計、住民、税務、国保、生活環境、介護保険、保健、高齢者、建設、産業、社会教育、学校教育関係
| [備考] 4ヶ町村で実施している独自の各種事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下にならないように留意しながら、合理化・効率化に努める必要があり、その調整方法がまとまり次第、随時、協議会に提案される。 |
|