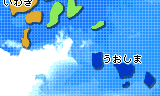|
 |
 |
 |
 |
 |
自主的な市町村合併を積極的に推進することを目標として、合併特例法が平成11年7月に改正され、交付税の優遇措置、合併特例債、地域審議会、住民発議制度、議員退職年金等の特例措置が大幅に拡充された。
これは、「向こう5年以内(2005年3月末日まで)に市町村合併をする場合、そのために国は十分な支援をする。」というものであるが、期限付きであり、法の再延長はないとされていることから、急激に合併論議が高まってきた。
また、県でも平成13年2月、市町村合併推進要綱を策定し、合併を支援する体制を整えている。
しかし、なぜ今、市町村合併が必要とされているか、その背景についてみていきたい。 |
 |
 |
 |
 |
| 1 |
地方分権等に対応する行政能力の強化(分権の受け皿づくり) |

| (1) |
広域的対応の必要性の高まり |
| |
住民の日常社会生活圏の拡大(徒歩、自転車から自動車へ)により、地理的な意 味で広域的に対応しなければならない問題が出てきたが、交通情報手段の発達からそれが可能となる条件が整ってきた。
さらにより豊かな生活を送るために住民の行政サービスへのニーズの増大(生涯学習等)や介護保険制度の導入等によって、市町村が取り組むべき仕事は、質・量ともに拡大している。これに適切に対処するためには、小さな町村では確保することが難しいより専門的で企画能力を備えた職員が必要となる。
|
| (2) |
地方分権の推進 |
| |
地方分権の目指すものは、「地域のことは地域で考え、判断し、地域の責任で施策を実施する。」という市町村の自主性を高めることである。
しかし、市町村の自主性が高まるということは、市町村ごとの財政力、資源、人材に応じて行政サービスに格差が生じることにもなる。今までのような「国・県の指導(基準)に従っていれば全国どこでも一緒」ということはなくなる。地域ごと、市町村ごとの特色を生かし自己決定・自己責任が原則の地方分権の時代には、市町村の役所で政策を自ら立案し、それを議会・住民にわかりやすく提示しつつ理解を求めることが出来る能力やそれを可能にする財政基盤が必要となる。
|
| (3) |
人口の少子・高齢化の進展 |
| |
少子化によって、日本全国の人口は2008年から減少に転じ、現在の人口1億2600万人が2050年には約1億人になるといわれている。65歳以上人口の割合が3割を越える市町村は、現在の1割弱程度から、2025年には約6割になるとの見通しもある。少子・高齢化の進展は経済に悪影響が出る一方で、医療、福祉等社会保障関係費をさらに増大させ、財政力の弱い小規模町村ほどその影響が大きくなってくる。 |

平成12年度末の国・地方を合わせた債務残高は約666兆円といわれている。
かつて平成9年度末頃に国債残高が260兆円に達すると危機感を募らせ、財政構造改革の必要性が叫ばれてきたが、好転するどころか、恐ろしい勢いで増加している。
地方も苦しいが、国も財政難にあえいでおり、国から地方への財政負担を減らしたいというのも、地方分権や市町村合併の背後にあると考えられる。
ここで地方交付税の仕組みについてふれてみたい。
税収入の少ない市町村には、国から地方交付税交付金が分配され、財政バランスを調整している。上島地区の各町村では、歳入総額の概ね40%〜50%近くをこの交付税に依存する状況が続いており、町村財政は、この交付税によって支えられ、成り立っているといっても過言ではない。
この交付税であるが、国が地方に分配する際、財源としての入口ベースが概ね13兆円、実際に分配する出口ベースが21兆円、不足する8兆円は交付税特別会計で借入れ、将来、国・地方で半分ずつ払っていこう、という仕組みで、当面の負担
を毎年度将来に先送りすることで凌いできた。
しかし、この借入れ金が累積し(借入金総額:12年度末34兆円)、交付税制度、さらには地方財政計画自体が成り立たない状態となりつつあるといわれており、「交付税の3割カット」さえ現実味を帯びてきた。
(いわゆる アメとムチ)
また、この交付税を別の角度からみてみよう。
今回改正された合併特例法に基づき、市町村が合併する場合、各種の支援措置が設けられている。合併準備補助金、合併市町村補助金、合併特例債、地方交付税の優遇措置(10年間の旧交付額保障)等である。
総務省は、「交付税問題と合併を絡めて考えるのは間違いである。」としているが、これらはいずれも、限られた交付税の総枠の中で合併団体に対して振り向けられるわけであるから合併を望まない、或いは、でき難い(できない)団体は当然、交付税の二重の減少という形にならざるを得ない。地理的状況等により、合併したくともし難いケースもあり、その場合、結果的にムチだけになることも、また、あり得る。
(危機管理として、その準備を)
こうした社会情勢の変化や財政状況の悪化に対応するため、市町村合併は、自治体の行財政基盤の強化を図る「有効な手段の一つ」といえるし、状況の変化に合わせて、好むと好まざるにかかわらず、危機管理として、合併問題に関する準備が必要であると思われる。
「合併するしないにかかわらず、交付税カットの時代が来る。これからは、いつか誰かが何とかしてくれるだろうという認識でいれば近い将来大変なことになる。
これからは合併問題は避けて通れない。危機意識をもって前向きに検討を。」
これは、平成12年10月29日、松山市で行われた「市町村合併をともに考える全国リレー総括シンポジウム」での自治大臣の話である。
合併問題は行政サイドだけで考えるものでは無論ない。
各町村としてもいろいろな形で情報を提供し、意見を取り入れながら研究し、共に考える環境づくりを整えつつ、この問題に取り組んでいかなければならない。 |
|
 |