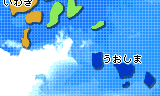|
交通網の発達などにより住民の日常の生活圏そのものが拡大し、広域的な施設利用が可能となったため、合併によって、スポーツ施設・文化施設等が効率的に配置され、狭い地域で類似施設を重複して設置する必要がなくなるというものです。
また、規模のメリット(スケールメリット)を生かして、これまでの人口規模、財政規模などから対応が困難であった施設整備やサービスの提供に取り組むことも可能であるというものです。
通常、こうした行財政の効率化は、市町村合併のもたらす最大の効果の一つといわれていますが、上島地区の場合は、それぞれの町村が非架橋の離島という地理的な条件から、「何時でも、誰でも、どの施設でも自由に」といった施設利用は架橋が実現しない限り制約が大きく、逆に、アンバランスを解消するために施設整備の二重構造を生み、こうした意味の合併効果はほとんど無いといわざるを得ません。
上島架橋が実現し地理的に一体化すれば、こうした二重構造の問題も解消されるでしょうが、架橋実現には非常に多くの経費と時間を必要とします。ですから当面は各島を結ぶ航路を充実させることによって対応せざるを得ませんが、併せて、上島架橋の早期実現に向け、地域の一体となった取組みが必要であると考えられます。
※スケールメリット……単位当たりの費用が経営規模の拡大につれて低下すること |
|