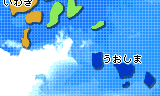|
新設合併の場合 |
編入合併の場合 |
に地
よ方
る自
原治
則法
|
合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後50日以内に新たな議員の選挙を行なう。 |
編入する市町村の議員の身分には変動がなく編入される市町村の議員はその身分を失う。
ただし、合併後の議員定数が増加することになれば、合併後50日以内に増員選挙を行なう。 |
| 合併特例法による特例 |
定数の特例 |
合併する前の市町村の協議により、次回の選挙までに限り、法定定数の2倍以内の範囲で議 員定数を増加することができる。
(50日以内に選挙を行う。) |
合併する市町村の協議により、編入する市町村の定数(合併前の定数)に人口比率を乗じて得たた数を加えて編入される市町村ごとの定数とし、それぞれ編入される市町村ごとに増員選挙を行う。(50日以内)
この場合、編入する市町村の議員の身分には、変動がない。 |
編入合併の場合には、合併時に左記の「定数の特例」により増員選挙を行うこととするとき又は「在任の特例」により引き続き議員として在任することとするときは、合併後、最初に行われる一般選挙により選出される議員の任期相当期間についても定数の特例を用い編入される合併関係市町村の区域ごとに選挙区を設け増員選挙をすることが出来る。
|
| 在任期間の特例 |
合併する市町村の協議により、合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間、引き続き在任することができる。 |
合併する市町村の協議により、編入される市町村の議員が、編入する市町村の議員の残任期間そのまま引き続き在任することができる。
|