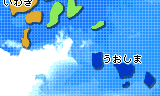|
平成10年度から3年間かけて、国から自治体に配分する地方交付税の算定方法を見直し、人口が4,000人未満の町村への配分が削減されました。
見直しの理由として、総務省は
1 規模の小さい町村では人口の少なさと経費増の関係が必ずしも顕著ではない。
2 小規模自治体では職員が役職を兼務するケースが多く、標準的な職員配置を 規定した交付税配分は実態に合わない。
などをあげています。
例えば、この算定方法が継続された場合、弓削町は平成13年度の交付税算定から、国勢調査人口の減少によって新たにこの要件に該当しますから、この見直しの要因だけで、前年に比べ約2千万円程度交付税額が減額となりました。
なお、生名村、岩城村、魚島村は、平成10年度から3ヶ年にわたって、実際に配分額が減額されました。
この交付税減額措置は、小規模町村の合併促進がねらいではないかともいわれています。 |
|