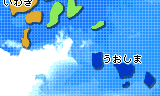|
住民が自分の住んでいる地域を把握し、地域の運営に直接参加できる程度の規模は、人口数万人程度ではないかと言われています。市町村が住民に最も身近な自治体であるという本来の特色が最もよく発揮できるのは、市町村がその程度の規模において可能ではないかと思われます。
そうすると、人口数十万、あるいは数百万というような大都市では、一体どうなるのかという疑問が生まれます。確かにそれらは巨大過ぎて、住民自治の場としては不適切です。そこで、その欠陥を補う方法として、区に分割して住民の参加を可能にするという方法がとられています。
ところで、逆に人口が少ない場合を考えてみますと、県の合併推進要綱では、「福祉、教育、環境等の分野において独立した住民サービスが提供でき、かつ、まちづくり等の分野でも一定の行財政能力の向上が期待される最低限の規模を確保するため、人口1万人を十分上回る組合せを原則とする。」としており、国の指針においても「合併の類型は、少なくとも人口1〜2万人程度の規模が期待される。」としています。
上島地区の場合、4ヶ町村の人口は8,605人で、最低限の人口規模さえ満たせません。
自治体の数が4分の1に減るということに妥協点が求められていますが、いずれにしても非架橋の離島という地理的条件は、合併効果の面で大きな阻害要因であると言わざるを得ません。
また、例えば県の示した基本パターン、今治市と越智郡全体が合併した場合は人口189,235人となりますが、上島地区は地続きでなく、ここでも地理的条件は高いハードルであることには違いがありません。 |
|