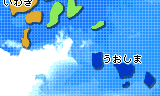|
 |
 |
面積 |
全体
|
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
| 30.29km2 |
11.76km2 |
3.87km2 |
11.49km2 |
3.17km2 |
|
 |
人口・世帯数 |
(平成12年国勢調査) |
項 目
|
全 体
|
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
| 人口 |
8,605人 |
3,858人 |
2,124人 |
2,289人 |
334人 |
| 世帯数 |
3,645世帯 |
1,670世帯 |
865世帯 |
933世帯 |
177世帯 |
|
 |
議会議員 |
( )内は定数 |
全体
|
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
| 43人(44) |
13人(14)
|
12人(12) |
12人(12) |
6人(6) |
| 任 期 |
平成15年7月14日 |
平成18年10月14日 |
平成15年4月29日 |
平成15年4月29日 |
|
 |
職員 |
( )内は一般行政職数、(平成14年度定員管理調査) |
全体
|
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
| 216人(147) |
80人(55)
|
55人(35) |
59人(47) |
22人(10) |
|
 |
財政 |
(平成13年度決算統計) |
| 項 目 |
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
| 財政(歳入) |
3,210,170千円 |
1,415,350千円 |
1,952,354千円 |
1,315,868千円 |
| 財政力指数 |
0.148 |
0.114 |
0.214 |
0.045 |
|
 |
上島地区の現状と課題 |
- (1)過疎化と少子・高齢化の進行
- 上島地域は弓削町(3,858人)、生名村(2,124人)、岩城村(2,289人)、魚島村(334人)の4町村で構成され、合計では8,605人であるが、昭和60年以降の海運造船業界の不況により急速な減少に転じ、昭和35年のピーク時の14,743人に比べ41.6%の大幅な減少となった。過疎化は現在も歯止めがかかっていない。
※( )内平成12年国勢調査人口
- (2)地域経済の衰退による活力の低下
- 上島地区の産業をみると、魚島村以外は概ね似通った産業構造を示しており、広島県因島市の造船関連業の発展と共に都市型の産業構造を形作ってきた。こうした外部依存型の経済体質ゆえに長引く構造不況の波をもろに被り、昭和60年以降、若年労働力の流出と地域活力の低下を招き、未だそうした状況から脱し切れていない。
その他、柑橘栽培を中心とした農業、養殖漁業、刺し網・定置網等の水産業があるが、いずれも小規模で、市場価格や天候に左右されやすく不安定な経営が続いている。
- (3)生活基盤等、社会資本整備の遅れ
- 上水道は、広島県からの「友愛の水」の分水が実現し、平成元年からの全域給水開始により慢性的な水不足は根本的に解消された。
下水道についても、魚島村はすでにコミュニティプラントとして整備
済みで、その他の町村においても、特定環境公共下水道や農業集落排水
等の制度を活用し整備を進めている。
しかし、いずれも事業規模が小さく、経営効率の面で将来の財政負担が懸念されているところである。
道路整備については、各町村の密集した集落内では、県道でさえ離合が困難な所が多くあるなど、未改良箇所が多く、本土に比べ整備の遅れが目立っている。
ごみ処理施設は、施設の老朽化や島外搬出経費の増加、ダイオキシン
問題等、早急に解決しなければならない多くの課題を抱えている。
また、弓削町や生名村では、公営住宅の老朽化による更新整備が急がれる。
- (4)乏しい自主財源と厳しい財政状況
- 各町村とも多くの行政課題を抱え厳しい財政事情が続いているが、いずれも財政規模が小さく、行財政基盤の強化という合併の主要目的についても、その効果はあまり期待できない。
歳入総額に占める自主財源の割合は、弓削町21.9%、生名村16.6%、岩城村24.5%、魚島村22.6%で、上島4ヶ町村平均で21.4%にすぎず、このことは逆に、国・県への依存の高さを示すもの
で、弾力性と安定性に乏しく、今後のまちづくりの困難性を表している。
※%は平成13年度決算統計
- (5)地理的条件による交通利便性の不足
-
平成11年度の瀬戸内しまなみ海道の開通は、日常生活航路の縮小・
廃止による交通利便性の低下を招き、上島地区の離島性をさらに強める結果となった。このことは、特に交通弱者といわれる人々の通勤、通院等に顕著に表れた。
上島4ヶ町村が合併した場合、行政区域内の一体的発展と離島性の根本的な解消を図るため、上島架橋の早期実現としまなみ海道への連結へ向け、地域一丸となって取り組んでいく必要があるが、架橋には多くの年数を要するため、既存航路の充実を図ることはもとより、新たな行政
区域内を結ぶ航路の確保が欠かせない。
|
|
|
 |