もったいない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう
![]() 「食品ロス」てなに?
「食品ロス」てなに?
◆まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことです。◆
日本国内における年間に捨てられる食品の量は、日本の食料消費全体の3割に当たる2,800万トン

このうち、売れ残りや期限を超えた食品、食べ残しなど、本来食べれたはずの、いわゆる「食品ロス」は約632万トンとされています。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた政界の食料援助量を大きく上回る量です。
また、日本人一人当たりに換算すると、『お茶碗約一杯分』(約136g)の食べ物が毎日捨てられる計算となります。

![]()

日本の食料自給率は現在39%(平成27年度)で、大半を輸入に頼っていますが、その一方で、食べられる食料を大量に
捨てているという現実があるのです。みなさん、もったいないと思いませんか。
![]() 「食品ロス」は様々な場面で発生 約半数は家庭から
「食品ロス」は様々な場面で発生 約半数は家庭から
「食品ロス」は、食品メーカや卸・小売店、飲食店、家庭など、「食べる」ことに関係する様々な場所で発生しています。
家庭においても食品ロス全体の約半数にあたる年間約302万トンが発生しています。食材別にみると
- 1位・・・ 野菜

- 2位・・・調理加工品

- 3位・・・果実類

- 4位・・・魚介類
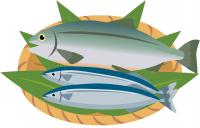
などが挙げられています。
・家庭から出される生ごみの中には、手つかずの食品が2割もあり、さらにそのうちの4分の1は賞味期限前にもかかわらず捨てれているものです。
・そのほか、調理の際での、野菜の皮むきや肉の脂身を取り除きなど、食べられる部分を過剰に捨てていることも食品ロスの原因になっています。
![]() 食品ロスになっているもの
食品ロスになっているもの
【家庭】 ・調理の際に食べられる部分を捨てている
・食べ残し 302万トン
・冷蔵庫などに入れたまま期限を超えた食品 など
【食品メーカ】 ・定番カット食品や期限を超えた食品などの返品
・製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品
【小 売 店】 ・新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された食品 330万トン
・客が食べ残した料理
【飲 食 店】 ・客に提供できなかった仕込み済の食材
・家庭での食品ロスを削減できれば、食べ物の廃棄量を減らすことができ、環境面・家計面にとっても
メリットがあります。
![]() 削減の工夫(1)食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」
削減の工夫(1)食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」
- 値段が安いからといって買い過ぎない。
- 買い物前に、冷蔵庫をチェックして同じ食材を買わない。
![]() 削減の工夫(2)残った食材は別の料理に活用
削減の工夫(2)残った食材は別の料理に活用
- 料理レシピサイトなどを利用して、食材を無駄にしない 。
- 中途半端に残ったら別の料理に活用する。
![]() 削減の工夫(3)「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解
削減の工夫(3)「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解
![]() 加工食品には、「消費期限」か「賞味期限」が表示されていますが、皆さんはご存知ですか?
加工食品には、「消費期限」か「賞味期限」が表示されていますが、皆さんはご存知ですか?![]()
- 「消費期限」は品質の劣化が早い食品に表示されている「食べても安全な期限」のため、それを超えたものは食べ
ないほうが安全です。
- 「賞味期限」は、品質の劣化が比較的遅い食品に表示されている「おいしく食べられる期限」であり、それを超えてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を超えた食品については、見た目や臭いで個別に判断しましょう。
![]() 削減の工夫(4)外食事での食べ残しを防ぐために
削減の工夫(4)外食事での食べ残しを防ぐために
- 小盛メニューがあれば利用する。
- 料理を注文するときに、食べきれないと思ったときは、「少なめにできますか?」とお願いする。
- セットメニューの中に食べられないものがあれば、注文の際に、あらかじめ抜いてもらう。
以上が『食品ロス削減』=『年間大量に捨てられていく、もったいない食品を減らす事』に繋がります。
皆さんも毎日の生活の中で『食品ロス』という言葉を思い出し、食品ロスを減らすことにより、上島町の環境、ひいては地球環境を考えていきましょう。